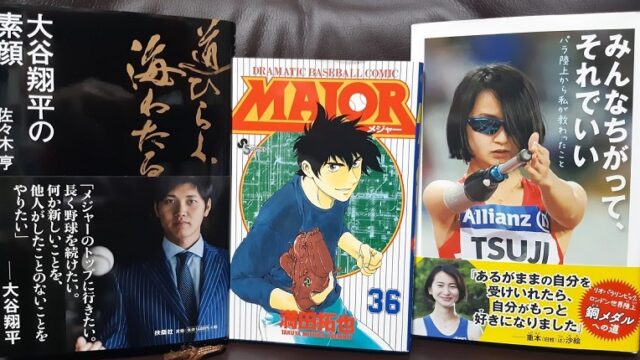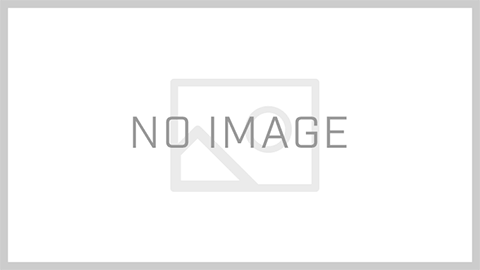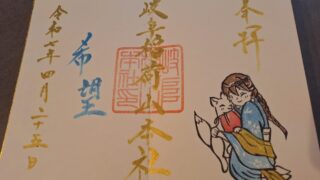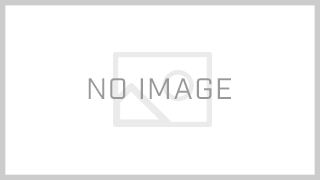こんにちは、ゴローです。
本日の記事では、ドラマ「19番目のカルテ」の名言・名シーンについて書いていきます。このドラマの予告が解禁された時から、ずっと楽しみにしていたドラマでした。
現在の日本医療は、「脳神経外科」「精神科」「整形外科」といったように、臓器ごとに18の専門分野に分けられているわけですが、それがゆえに現代医療の限界を感じずにはいられないことも事実です。
そこで、19番目の新領域として期待されているのが「総合診療科」です。医療において、ある意味一番大切である、この「総合診療科」にスポットを当てたのが今回のドラマです。
僕自身、自分が病気をしたことで総合診療科の必要性を実感してきました。自分も含め、いろいろな病気の方を見てきた中で、既存のやり方では現在の病気をなくしていくことは難しくなっていると感じます。
数多くの病院を、そして各科をたらい回しになるドクターショッピングを経験している方があまりにも多いのが現状です。病気になる背景は人それぞれであり、外科的手術が必要な病気以外のほとんどは、「その人」を真剣かつ細かく見ていかないと、治すことの出来ないものばかりではないかと思います。
そのため、小芝風花さん演じる滝野先生のように、細分化された専門領域で、それぞれの専門を極めることを是とする現在の医療のシステムに疑問やギャップを感じている医師も最近では増えてきているわけです。
だからこそ、「病気を診る」のではなく、「人を診る」医療・医師が必要となってくるわけで、松本潤さん演じる徳重先生のような存在や、総合診療科の重要性を感じさせてくれるドラマとなっています。もっと言うと、病気を治すためには、医療だけではなくいろいろな幅広い分野や個人の持つ背景など、多角的に考えていく必要があり、現代医療に対して一石を投じているのがこのドラマであり、漫画の原作者である富士屋カツヒトさんの想いではないかと思っています。
総合診療科にスポットを当てた漫画を書かれた富士屋さんは、きっと優しい方なんだろうなと、このドラマを見ていて思わずにはいられません。
そして個人的にはもう1つ。登場人物の名前が全て愛知県の地名になっているというのが、この地方在住の人間としては面白いです。愛知県在住の方なのかな?主役2人の名字を考えると、あの辺りに住んでいる方なのかな?なんて想像も膨らんでしまいます(笑)
それでは、前置きが長くなってしまいましたが、具体的にこのドラマの名言・名シーンについて一緒に見ていきましょう!10年間、自分自身も病気を経験している人間だからこそ書けた文章になっていると思います!
Contents
松本潤(徳重晃)→仲里依紗(黒岩百々)への言葉

それくらいじゃありません。
痛みを感じ、事実、生活に支障が出ている。
それは、大したことだと、僕は思います。
終始一貫して優しい徳重先生にとって、まさに代表的な言葉かと思います。とにかく患者に寄り添ってくれるからこそ、心から出てきた言葉なのだと思います。
患者の黒岩さんがどれだけ苦しんでいても、痛みや辛さが数値に表れるわけではないので、周りの誰も(他の多くの医師も含めて)理解してくれません。そんな日々を過ごしていくうちに、黒岩さん自身からも思わず、「大したことないのに」という言葉が口からつくほど、ある意味追い詰められてしまっているわけです。
だからこそ、表には出てこない患者の本当の辛さを理解してくれる徳重先生のこの言葉は嬉しかったのだと思います。
僕自身も、言葉に出来ない痛みとか苦しさを味わってきているので、理解してくれる方がいることのありがたさは分かります。何時間もずっと失神しそうな感覚とか、他人には分かりませんよね?たとえ同じ病名であっても、本当の意味で理解し合えることは難しいと思うんですよね。だからこそ、ただ寄り添ってくれるだけでいいのだと思います。
松本潤(徳重晃)→小芝風花(滝野みずき)への言葉

黒岩さん、鎮痛剤飲んでたね、効かないのに。
きちんと飲んでた。それは、どうしてなんだろう?
徳重先生から滝野先生への投げかけ。1つの事象をヒントに、何か少しでも分かることはないかという姿勢が、まさに総合診療科の真骨頂。そして、後輩の滝野先生を育てるために、答えを言うのではなく質問を投げて考えさせるという、徳重先生の資質を感じます。
効かない・・・、それでも飲む。
黒岩さんは本当に治したいから。
自分の痛みを。嘘じゃなく。
徳重先生の投げかけに対して、滝野先生の考察がこちらです。徳重が「効かないのに」薬を飲んでいることに注目できたこと、そして、滝野が「本当に治したいから」という視点に氣付けたこと、2人の医師が患者に本氣で寄り添っているからこその、やり取りであることがうかがえる名シーンだったと思います。
患者に寄り添っていない医師であれば、ムダに薬を出し続けるだけで終了だったと思います。僕自身も、「効くことのない」痛み止めや、「症状が改善しない」薬を何百錠飲んできたことか・・・、でもそれは、藁にもすがる想いだったから。何でもいいからチャンスがあるのであれば!なんとか病気を治したい!という想いがあったからこそ(発症当時は、病気を治すためのいろいろな「可能性・選択肢」を持ち合わせていませんでしたからね)。
※この名シーンの話とは別に、現在の医療は薬に頼りすぎであり、必要の無い薬を飲み続けしている人が多すぎるので氣をつけて下さいね。
松本潤(徳重晃)→仲里依紗(黒岩百々)への言葉

検査の結果ですが、やはり異常は認められませんでした。全ての検査で、異常があがってこなかったという事実によって、1つの診断ができます。
それは、線維筋痛症。
この病気のやっかいなところは、痛みが出た部位を検査しても、異常が出ないことなんです。
そこで今回は、18の圧痛部位の確認と問診を行いました。リウマチ・膠原病などの疾患との区別もつきました。他の疾患の可能性は、極めて低いです。
黒岩さんが感じている痛みは、れっきとした病名のある病気です。
最終的に、黒岩さんの病名は「線維筋痛症」と診断がつきました。現在の西洋医学では、検査や数値に異常が無いと病名をつけることができないという弱点がありますが、そこを逆手にとった、徳重先生の見事な診察でした。
そして何より印象的だったのが、「やっとこれで、病気だって言える!」という、仲里依紗(黒岩さん)の嬉しそうな、安心したような表情が忘れられないですね。病名がついて嬉しいなんて変な氣もしますが、症状だけがあって診断がつかない宙ぶらりんな状態ってめちゃくちゃ精神的にも辛いんですよね。すごく共感したシーンでした!
松本潤(徳重晃)→仲里依紗(黒岩百々)への言葉
ありがとうございます。
黒岩さんが痛みと向き合い、諦めないでくれたから、
この診断にたどりつけました。
この言葉が続けて出てくる徳重先生は、とんでもない人格者だと思います(笑)医師としてとかではなく、人間的にすごいですよね。
自分の病気を見つけてくれただけでも嬉しいことなのに、自分のこれまでの頑張りを認めてもらえたようで、黒岩さん(患者)にとっては嬉しい言葉であったと思います。
と同時に、この記事を読んでくれている方の中に、同じように病名がつかずに苦しんでいる方がいるのなら、自分の出来る範囲で諦めずに頑張ってほしい!って思います。きっとどこかに、患者のことを、患者の症状のことを、肯定して見つけてくれる方が現われると思います、その時まで諦めないでいてくれたら嬉しいです。
参考までに、僕の経験を書いた記事も貼っておきますね。


松本潤(徳重晃)→小芝風花(滝野みずき)への言葉

何を食べ、何を習慣にし、どうやって今日まで生きてきたか。
その人の生きた過程を知らなければ、診断はつけられない。
僕たちは、病気じゃなくて、人を診てるんだから。
病気を診るのではなく「人を診る」!
この言葉こそが、徳重先生の、総合診療科の根幹となる部分であり、このドラマが伝えたいメッセージだと思います。
僕自身が病気になったことがきっかけで、なるべく先入観を持たずに、自分でもいろいろな角度から「病気」というものについて考えてきました。なぜ人は病気になるのだろう?同じ病気でも、治る人もいれば治らない人もいるのはなぜだろう?それこそ、僕自身10年間も病人をやっているわけですがなぜだろう?といった具合です。
そんな中で、たどり着いた答えの1つが、徳重先生の言う「人を診る」ことの重要性です。結局、病気を診ているだけでは、病気はなかなか治らないということ。同じ病名であっても、治らない人がいるというのは「人それぞれ」病気になる理由が違うから。ということは、人によってそれぞれ治療法は変わってくるはずであり、治っていく過程も変わってくるわけです。
とはいうものの、西洋医学の性質上、「全ての治療が、同じ条件下で再現可能であること」が求められるため(「病気」を診ざるをえない)、ここに西洋医学の限界があると言わざるをえないわけです。
だからこそ、患者の病気を治したい!と本氣で考えている医師ほど、葛藤を抱えることになってしまうはずであり、総合診療科というものの必要性が出てきたのだと思います。
まだまだ課題は多いと思いますが、「その人が生きてきた過程」や生活習慣・家庭環境など、問診を中心に粘り強く(もちろん患者側も含め)病気をなくしていけたらいいですよね。そのためには、西洋医学とか東洋医学とかいう枠ではなく、いろいろなジャンルの人が横に繋がって&広がっていくことが、今後必要になってくるのではないかと思います。
小芝風花(滝野みずき)→杉田雷麟(岡崎拓)への言葉

緊張して手が震える、恐いおもいをして足がすくむ。
そうゆうことありませんか?
想像しているより人の心、脳と身体は繋がっています。
たく君の足が動かないのは、それと同じです。
無意識のうちに、脳が身体にブレーキをかけている。
これを、「機能性神経症状症」と呼びます。
脳や神経の働きには異常がないにもかかわらず、しびれ・歩行困難・視覚の問題など、神経症状が生じる状態を「機能性神経症状症」と呼びます。この場合の患者の拓くんは、神経に問題が無いのに、歩くことが出来ない、立つことが出来なくなりました。
そんなことあるの?と思われるかもしれませんが、僕自身も何度も味わっています。突然手が動かなくなって、箸を持っているのに、ご飯を口まで運ぶことが出来ない・・・なんて経験もしてきました。
今なら一種の自己暗示がかかってしまったであろうこと、脳が身体にブレーキをかけてしまっていることも理解できます。でも当時は慌てたなあ、だから余計にはまっていってしまうという悪循環なんですけどね。
今回のドラマの場合は、滝野先生・徳重先生を中心に、「僕の足はここにある!立つことが出来る!」といった確認作業を患者にさせることにより、最終的には自力で立つことが出来るようになっていきました。
このシーンって実はすごく大事なシーンで、僕自身これまでいろいろな事例や勉強を重ねてきて、病気のほとんどは脳と身体の繋がりにあると感じています。脳をうまく利用して、潜在意識レベルで納得することが出来れば、正直自分の病気も治っていくチャンスがあると思っています。だからこそ、ドラマでもこのシーンが描かれていたはずです。
こういったことはリアルな現場でもあることで、総合診療科を立ち上げた第一人者である、生坂政臣医師をピックアップした情熱大陸を見たことがあるのですが、そこでも車椅子に乗っていた少年が、脳のブレーキを外したことで急に歩き出すというシーンがありました。今回のドラマの事例と似ているので、ひょっとしたら生坂政臣さんがドラマの監修に関わっているのかもしれませんね。
いずれにせよ、脳のブレーキを外していくことで、病気や障がいが治っていったという事例を多く見てきましたし、知り合いの治療家からも何度も聴いたことがあるので、自分も含めて皆さんにも希望は持っていてほしいです!
松本潤(徳重晃)→ファーストサマーウイカ(茶屋坂心)への言葉
無いと思います。医学的に、「心」という臓器はありません。
それでも人は、響き合う。
好きな人を見た時、胸は高鳴り、誰かに傷つけられた時、瞳はうるむ。
あなたと私、その間に心は生まれると、僕は思っています。
茶屋坂先生に、人の「心」はどこにあると思う?と質問された時の徳重先生の返答がこの言葉です。「人を診る医師」である徳重先生らしい言葉だなと思います。
医学的には心はありません。でも、理屈(医学)を超えた部分で、身体や心は反応しているわけです。意味も分からない涙が出てくることってありますよね?なんかここに居ると氣持ちがいいなあ、逆にいやだなあとかありますよね?
先ほどの、脳と身体が繋がっているのと同じで、心もまた繋がっているわけですね。あなたと私の間に心が生まれるということは、結局、広い意味での人間関係が大切でもありますし、1人や2人でも信頼できる人物が存在するだけで氣持ち(心)も楽になるわけですよね。
田中泯(赤池登)の言葉

このままいくと、患者は、病名でしか扱われなくなるぞ。
医療は、ただの技術になり果てる・・・。
徳重先生の師匠、赤池先生の言葉です。
大学での講義をしているシーンとして、赤池先生が発していた言葉ですが、現在の医療体制への危機感として、赤池先生の魂の叫びとして飛び出した言葉・シーンでもありました。
これまで見てきたように、現在の医療体制では病人が増える一方です。それは、患者を「人」として診るわけではなく、病名でしか分類していないから。
病名でしか扱われなくなるぞ、という赤池先生の言葉はひじょうに重い言葉です。そして、「ただの技術」になり果てるという言葉には、赤池先生の嘆きともとれる感情が読み取れます。決められたことをしていくことはもちろん必要ですが、マニュアル一辺倒で治る病気って実は少ないですよね。それで病気が治るのであれば、こんなに病人が増え続けているわけがないですから。赤池先生の、そして作者やこのドラマ関係者の、「人を診る医療」の重要性を、改めて社会に投げかけている格となるシーンだったと思われます。